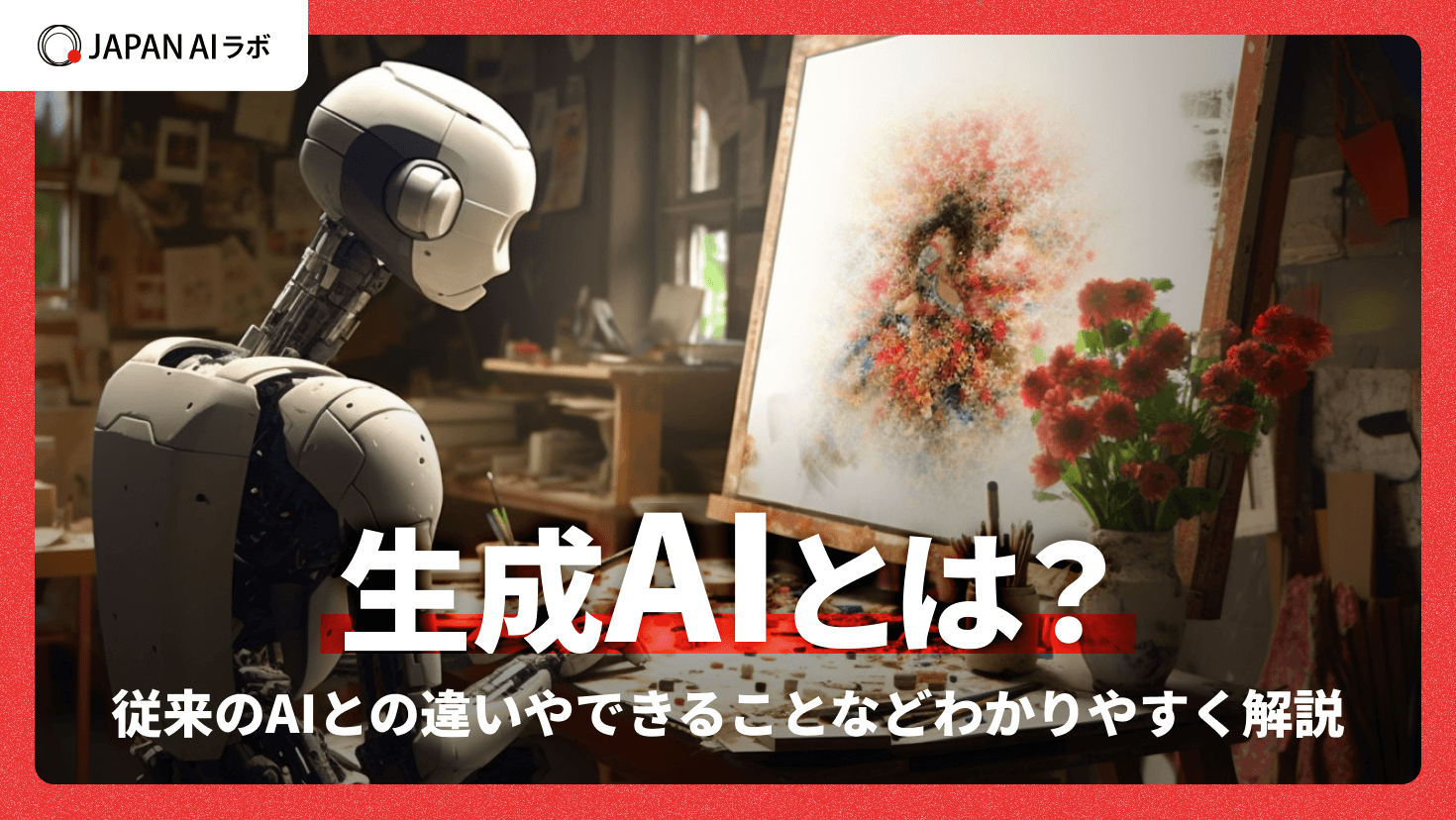基礎知識
ChatGPTが引き起こす情報漏洩のリスクとは?企業が取るべきセキュリティ対策を解説
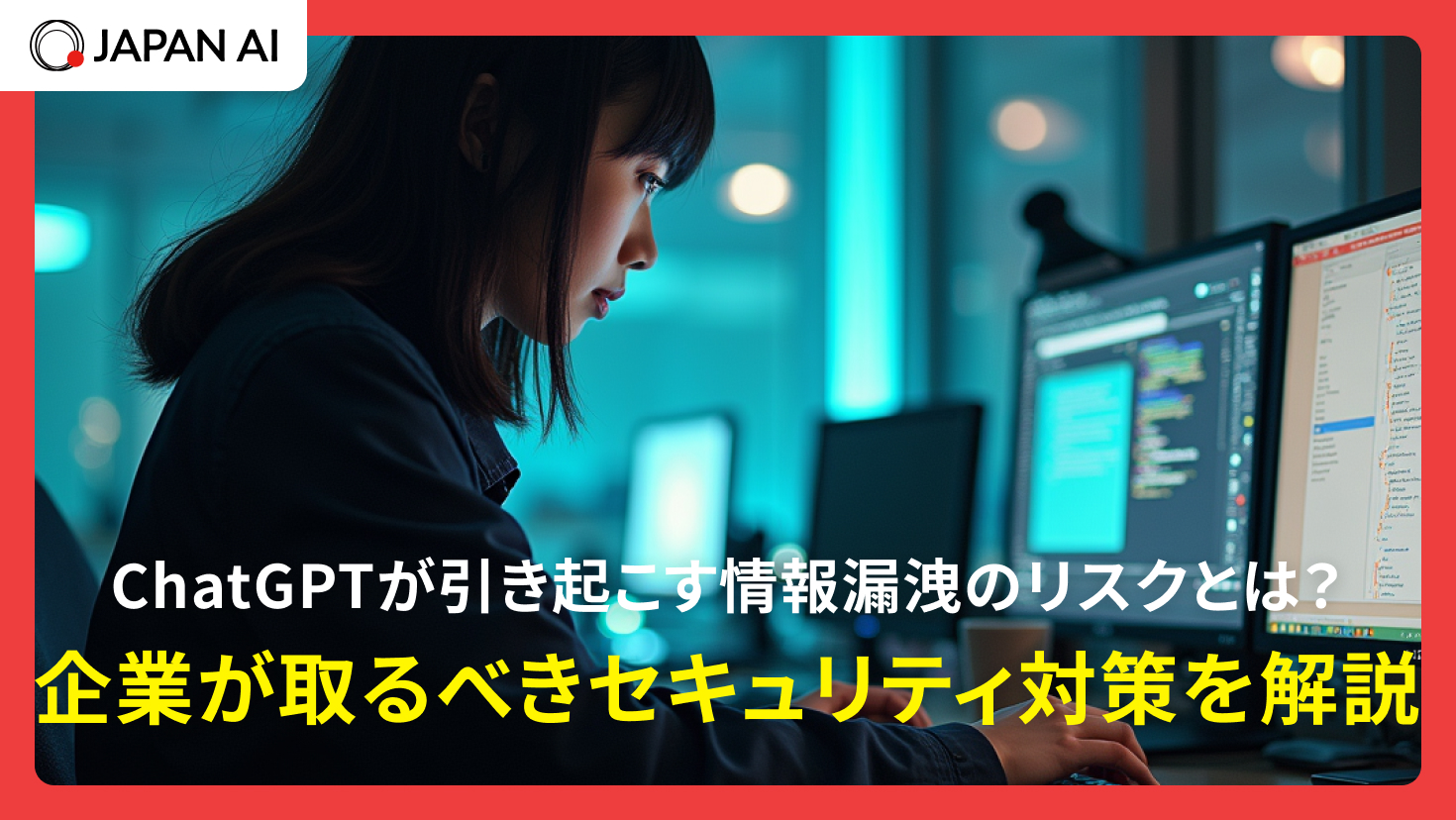
ChatGPTは、大規模なデータを基に自然な言語生成を行うAIツールで、さまざまな業務において効率化や生産性向上を支援します。日常的なタスクから高度な分析作業まで幅広く活用できることから、企業での導入が加速しています。一方で、情報漏洩や誤情報の発信、著作権侵害など、企業利用における特有のリスクが存在することも事実です。
本記事では、ChatGPTを企業で安全に利用するために注意すべきポイントや、具体的なセキュリティ対策について詳しく解説します。ChatGPTの特性を理解し、適切な運用ルールを整備することで、これらのリスクを軽減しながらメリットを最大限に引き出す方法を探ります。AIを効果的に業務に取り入れるためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むことで分かること:
- ChatGPTとはどのようなAIツールか
- ChatGPTを企業で利用する際のリスクと注意点
- 企業利用時に講じるべきセキュリティ対策
【2025年】法人向け生成AIサービスおすすめ15選を比較!タイプ別にご紹介
様々な業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」
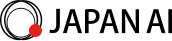
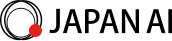
貴社業務に特化したAIエージェントを搭載!
上場企業水準のセキュリティ環境と
活用支援を無償で提供
チャットツールなら JAPAN AI CHAT
上場企業水準のセキュリティ環境
豊富なテンプレートをご用意
自社開発のRAGで高回答精度を実現
外部連携機能をご提供

ChatGPTに企業利用における3つのリスク

AIツールであるChatGPTを企業で活用する際には、多様なメリットが期待される一方で、見逃せないリスクが存在します。
ここでは、ChatGPT利用における3つの主要なリスクを詳しく解説します。
- 誤情報の発信
- 著作権侵害などの法的リスク
- 情報漏洩やセキュリティリスク
1. 誤情報の発信
ChatGPTは、大量のデータから生成された情報を基に回答を提供しますが、常に正確な情報を保証できるわけではありません。「誤情報の発信」や「誤字脱字」による混乱は、企業の信頼性を損なう恐れがあります。また、AI特有の「幻覚(ハルシネーション)」と呼ばれる現象により、現実には存在しない情報が生成されるリスクもあります。
さらに、フェイクニュースや誤解を招くコンテンツが生成される可能性もあるため、ChatGPTから得た情報は慎重に検証し、適切なフィルタリングを行う必要があります。
2. 著作権侵害などの法的リスク
ChatGPTが生成する回答には、著作権の保護を受けるコンテンツや個人情報が含まれる可能性があります。このような場合、知らずに第三者の著作物を使用することで「著作権侵害」のリスクが生じる可能性があります。
また、生成内容に不適切な個人情報が含まれていた場合、プライバシー侵害につながる可能性もあり、企業として法的責任を問われるリスクが存在します。ChatGPTを利用する際には、生成された内容を確認し、適切な法的対策を講じる必要があります。
3. 情報漏洩やセキュリティリスク
ChatGPTを利用する際、企業が提供したデータが外部に流出するリスクは見過ごせません。例えば、従業員が機密情報を入力した場合、そのデータがAIの学習プロセスに組み込まれる可能性があり、結果として外部流出のリスクを高める場合があります。また、不正アクセスやセキュリティの脆弱性が原因で、システムが攻撃を受ける場合も考えられます。
これらのリスクを未然に防ぐためには、次に解説する「ChatGPTを企業が利用する際の情報漏洩のリスク」を正しく理解することが不可欠となります。
Chatgptの法人契約とは?企業利用する際の料金やセキュリティリスクをご紹介
ChatGPTを企業が利用する際の情報漏洩のリスクとは

企業がChatGPTを導入する際には、情報漏洩に関連するリスクを考慮する必要があります。ここでは、情報漏洩のリスクとして特に注意すべき3つのポイントについて詳しく解説します。
- 不正なプラグインやマルウェアによるシステムアクセスの危険
- 知的財産権や個人情報の不適切な取り扱い
- データの外部流出のリスク
不正なプラグインやマルウェアによるシステムアクセスの危険
ChatGPTを外部サービスと連携して使用する際、プラグインの導入に伴うリスクが発生します。一見正常に動作しているように見えるプラグインでも、攻撃者が悪意を持って設計したものをインストールしてしまう可能性があります。
このような不正なプラグインを通じて、ユーザーが入力した個人情報や機密情報が外部に流出する恐れがあります。特に企業においては、重要なデータを扱う場面が多いため、プラグインの選定と利用時には十分な注意が必要です。信頼性のあるプラグインを選び、適切なセキュリティ設定を行うことが求められます。
知的財産権や個人情報の不適切な取り扱い
ChatGPTはインターネット上にある膨大なデータを基に生成を実施するモデルであるため、生成物が意図せず既存の著作物や他者のアイデアに類似するリスクがあります。また、個人情報を含むデータが生成され、意図せずプライバシー侵害につながる場合もあります。このような問題が発生した場合、企業の信頼性や評判に大きな影響を及ぼしかねません。
ChatGPTが提供する生成物を外部に公開する際には、次の点を必ず確認する必要があります。
- 生成物が既存の著作物を模倣していないか
- プライバシーに配慮し、個人情報が含まれていないか
これらの確認を怠ると、法的責任を問われる可能性があるため、企業内でのガイドライン作成や確認体制の構築が重要です。
データの外部流出のリスク
ChatGPTに入力した情報がAIモデルの改善に利用される場合がある点も、大きなリスクとなります。OpenAI社の公式声明によれば、API以外でのChatGPT利用時には、入力されたデータがモデル改善のために使用される可能性があるとされています。そのため、機密情報や顧客データをChatGPTに入力した場合、意図せずそれらの情報が外部に流出する危険性があります。
例えば、Amazonでは、ChatGPTが生成した内容に自社の未公開情報に似たデータが含まれていることを確認したと報告されています。こうした事例を防ぐため、企業がChatGPTを利用する際は入力データを厳密に管理し、機密情報の扱いに細心の注意を払うことが必要です。
ChatGPTを企業が利用する際のセキュリティリスク対策4選

企業がChatGPTを業務に導入する際には、セキュリティリスクを適切に管理することが不可欠です。
ここでは、企業が採るべき具体的な対策を4つ紹介します。
- データ保護対策の強化
- 知的財産権や個人情報保護の強化措置
- 不正プラグインやマルウェア対策の強化
- 高いセキュリティ環境を備えたツールを活用する
データ保護対策の強化
ChatGPT利用時の情報漏洩を防ぐためには、以下の2つの対策が有効です。
| ■機密性の高いデータを入力しない |
| 情報漏洩を防ぐ最も手軽で確実な対策は、ChatGPTに重要な機密データを入力しないことです。特に顧客情報や社内の極秘情報については、AIに依存せず慎重に管理する必要があります。機密情報を入力しないルールを社内で徹底することで、リスクを大きく低減できます。 |
| ■ChatGPT APIを活用する |
| OpenAIが提供するAPIは、入力データをモデルの学習に使用しない仕組みが採用されています。そのため、情報漏洩リスクを大幅に減らすことが可能です。ただし、APIを導入する際には、コストやシステムの整備が必要となるため、導入計画を明確に立てることが重要です。 |
知的財産権や個人情報保護の強化措置
企業が法的リスクを回避するためには、以下の3点を実施することが求められます。
| ■社内規則とチェック体制の構築 |
| 生成データの利用に関するガイドラインや確認プロセスを設けることで、意図せぬ法的トラブルを防ぎます。問題が発生した場合でも、迅速に改善できる仕組みを構築しておくことが重要です。 |
| ■法令やガイドラインの把握と順守 |
| 著作権やプライバシー保護に関する国内外の法律を理解し、適切に対応することが必要です。特にグローバル市場での利用を考える場合、地域ごとの規制を把握することが不可欠です。 |
| ■トレーニング・学習プログラムの導入 |
| 従業員への研修を通じて、著作権や個人情報保護に関するリテラシーを向上させます。これにより、組織全体でChatGPTを安全に利用する文化を醸成できます。 |
不正プラグインやマルウェア対策の強化
ChatGPTを外部サービスと統合する際には、次のような取り組みを行うことで安全性を向上させることができます。
| ■最新版のChatGPTを活用する |
| セキュリティパッチが適用された最新バージョンを使用することで、潜在的な脆弱性への対応が可能になります。 |
| ■信頼できる提供元からのみプラグインを導入する |
| 正規の配布元から入手したプラグインを利用することで、悪意のあるソフトウェアのインストールリスクを軽減します。 |
| ■リンク先の安全性を確認する |
| URLの信頼性をチェックし、不審なリンクを避けることで、意図しない被害を防ぎます。 |
これらの取り組みを継続的に実施することで、セキュリティリスクを未然に防ぎ、安心してChatGPTを活用できます。
高いセキュリティ環境を備えたツールを活用する
企業がChatGPTを含むAIツールを導入する際には、セキュリティが確保されたツールの利用が鍵となります。顧客情報や企業秘密など、流出が許されない情報を保護するため、上場企業レベルのセキュリティ環境を持つツールを選定することが推奨されます。こうしたツールを利用することで、リスクを最小限に抑えながらAIの利便性を活用できます。
ChatGPTのセキュリティリスクとは?懸念される問題と5つの対策方法を解説
ChatGPTの法人利用時のセキュリティリスクとは?5つの対策方法を解説
上場企業水準の高いセキュリティ環境の法人向けAIツール「JAPAN AI CHAT」

「JAPAN AI CHAT」は、企業の機密情報を安全に取り扱うために設計された、高度なセキュリティ機能を備えた法人向けAIツールです。
以下に、その主な特徴を紹介します。
- 暗号化された通信
- データの分離
- アクセス制限
- 定期的なセキュリティ監査
- 日本企業向けに最適化
| 特徴 | 解説 |
|---|---|
| ■暗号化された通信 | AIとの通信は強力に暗号化されており、第三者による情報の傍受や不正なアクセスを防ぎます。 |
| ■データの分離 | 顧客ごとのデータを厳格に分離して管理することで、他の利用者のデータと混在するリスクを排除し、情報漏洩のリスクを最小化します。 |
| ■アクセス制限 | 権限のないユーザーによるアクセスを厳しく制限し、機密情報が外部に漏れることを防ぎます。 |
| ■定期的なセキュリティ監査 | 最新のセキュリティ脅威に対応するため、専門チームによる定期的なセキュリティ監査を実施し、安全性を常に最適化しています。 |
| ■日本企業向けに最適化 | 日本の法律や規制に完全準拠して設計されており、国内企業が安心して利用できる環境を提供しています。 |
「JAPAN AI CHAT」は、企業の機密情報を扱うことを想定して設計されており、情報保護ニーズにハイレベルで応える信頼性の高いツールです。
貴社業務に特化したAIエージェントを搭載!「JAPAN AI CHAT」
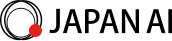
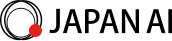
貴社業務に特化したAIエージェントを搭載!
上場企業水準のセキュリティ環境と
活用支援を無償で提供
チャットツールなら JAPAN AI CHAT
上場企業水準のセキュリティ環境
豊富なテンプレートをご用意
自社開発のRAGで高回答精度を実現
外部連携機能をご提供

ChatGPTを使用する時に注意しておくべきポイント

企業がChatGPTを活用する上で、その利便性を最大限引き出すには、注意すべきポイントを理解し、適切に対処することが欠かせません。ここでは、利用時に注意すべき3つのポイントについて解説します。
- 2021年までの情報が基礎となっている
- 日本語と英語で情報量に差がある
- 提供された回答をそのまま適用しない
2021年までの情報が基礎となっている
ChatGPTの学習モデルは、無料版の場合2021年9月までのデータを基に構築されています。有料版のモデルでも、最新情報にはアクセスできない点に注意が必要です。特にリサーチや市場調査で利用する際には、生成された情報が古い可能性を考慮し、必ず精査を行う必要があります。古いデータに基づく判断は誤解を招く恐れがあるため、最新情報は別途確認することを推奨します。
日本語と英語で情報量に差がある
ChatGPTは日本語でも多くの質問に対して正確かつ有用な回答を提供できます。しかし、日本語と英語では情報量や回答精度に差がある場合があり、質問の内容によっては、英語の方がより多くの情報や詳細なニュアンスに基づいた回答が得られる場合があります。例えば、特定の専門分野や海外の最新動向に関する質問などがこれに当たります。状況に応じて言語を柔軟に選択して活用するのも効果的な利用方法の1つと言えます。
提供された回答をそのまま適用しない
ChatGPTが生成する回答は、質問ごとに異なる内容が出力されるため、意図せずコピーコンテンツを作成してしまうリスクは比較的低いと言えます。
しかし、生成された文章が他のサイトや著作物と似通っている可能性は完全に否定できません。回答をそのまま使用せず、自分の言葉で表現をアレンジしながら活用することが推奨されます。このプロセスにより、オリジナル性を高めつつ、より効果的なコンテンツを作成することが可能です。
ChatGPTによる情報漏洩リスクまとめ

本記事では、ChatGPTを企業で利用する際に注意すべき情報漏洩リスクや、それらを回避するためのセキュリティ対策について詳しく解説しました。誤情報の発信や法的リスク、そして情報漏洩の可能性は、ChatGPTを活用する上で見逃せない課題です。また、適切な対策を講じることで、これらのリスクを大幅に軽減することができます。
特に、企業が機密情報や顧客データを安全に管理するためには、セキュリティ環境の整備が欠かせません。そのような中、JAPAN AI CHATは、これらのリスクを緩和するために設計された法人向けAIツールとして注目されています。暗号化通信やデータ分離、アクセス制限といった高度なセキュリティ機能を備え、日本企業のニーズに合わせた安心・安全な利用環境を提供します。
JAPAN AI CHATを活用することで、情報漏洩の不安を解消し、安心してAIツールを業務に取り入れることが可能になります。AIの利便性を最大限引き出すためにも、信頼性の高いツールを選び、適切な運用を心がけることが重要です。
【2025年】法人向け生成AIサービスおすすめ15選を比較!タイプ別にご紹介
様々な業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」
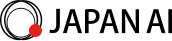
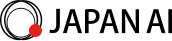
貴社業務に特化したAIエージェントを搭載!
上場企業水準のセキュリティ環境と
活用支援を無償で提供
チャットツールなら JAPAN AI CHAT
上場企業水準のセキュリティ環境
豊富なテンプレートをご用意
自社開発のRAGで高回答精度を実現
外部連携機能をご提供


AIを活用した業務工数の削減 個社向けの開発対応が可能
事業に沿った自社専用AIを搭載できる「JAPAN AI CHAT」で業務効率化!
資料では「JAPAN AI CHAT」の特徴や他にはない機能をご紹介しています。具体的なAIの活用事例や各種業務での利用シーンなどもまとめて掲載。
あわせて読みたい記事